公正証書遺言のリモート化(Web会議)について

【公正証書遺言のリモート化】
前回のブログで、遺言公正証書の電子化について触れましたが、今回は、改正公証人法のもう一つの柱である公正証書遺言のリモート化について説明します。
リモート方式による公正証書の作成は、公証人と列席者(遺言者、証人2名)が一堂に会さなくても、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識できる状況の下であれば、そのような状況の下での通話により公正証書を作成することを認めるもので、関係者(遺言者、証人、公証人)、中でも遺言者の利便性を高めるのが狙いです。日本公証人連合会では、公証人がMicrosoftのTeamsを 使って主催するWeb会議に列席者(遺言者、証人2名)が参加する方法で公正証書を作成する予定と聞いています。

【リモート方式による遺言公正証書作成の要件】
リモート方式により公正証書一般を作成するためには、3つの要件がありますが、遺言については単独行為のため、要件は事実上2つとなります。
(1)遺言者の申出があること
リモート方式の導入は、嘱託人(遺言者)の利便性向上のためのものですから、嘱託人が希望していない場合にまでリモート方式で行うことは適当でないからです。
(2)公証人が相当と認めること
公正証書の本質は、公証人が嘱託人(遺言者)の供述など公証人が実際に確認した事実を正確に記録することで、将来、その事実の有無や有効性が争われるなどの紛争の発生を予防することにあるため、利便性を過度に重視し、公証人による事実の確認がおろそかになるようなことがあって本末転倒だからです。公証人がリモート方式の必要性と許容性の両面から総合的に勘案の上、相当かどうかを判断します。
①リモート方式によることの必要性
リモート作成の必要性に関しては、嘱託人(遺言者)が公証役場に赴くことが困難な場合などが考えられ、 例えば、嘱託人の心身の状況や就業状況から公証役場に赴くことが困難である、離島その他の地理的な事情から公証役場へのアクセスが困難である、などが考えられます。
②リモート方式によることの許容性
一方、許容性については、公正証書の紛争予防機能に照らし、嘱託人の本人確認、真意の確認、 判断能力の確認等に支障がないかを諸般の事情に照らして判断することになると考えられます。遺言では特に慎重な判断が必要と考えられ、嘱託人(遺言者)の年齢や心身の状況、その他を勘案し、 事後的に紛争となる蓋然性が有る場合には、公証人が相当と認めない可能性も十分あります。
【リモート参加のための必要機材等】
リモート参加のためには、参加する列席者(遺言者、証人2名)において、リモート参加のために必要な機材を準備する必要があります。
①パソコン
スマホ、タブレットでもWeb会議に参加することはできますが、電子サインを行うときなどに必要となる画面の共有ができないため、電子公正証書の作成手続に使用することはできません。
②Webカメラ、マイク、スピーカー等
現在では、 パソコンに内蔵されていることがほとんですが、当該機能がないパソコンは別途準備する必要があります。
③電子サインのためにタッチ入力が可能なディスプレイ又はペンタブレットとタッチペン
公正証書に電子サインを行うために必要です。
④ メールアドレス
Web会議への招待メールや、リモート手続中に送信される電子サイン依頼メール等を受信するために必要です。
【リモート方式による遺言公正証書作成の流れ】
リモート方式による公正証書の作成についても、 嘱託人(遺言者)側から公正証書の作成を申し込み、公証人と嘱託人とのやりとりの中で公正証書の案文を確定し、公正証書の作成日時を決めることについては、現行と同じです。
①Web会議招待のメール
事前に証人からリモート参加を希望する列席者(遺言者、証人2名)に対し、Web会議招待のメールが送付されます。
②Web会議への参加と本人確認
公正証書作成当日、所定の時間に、 列席者(遺言者、証人2名)は、事前に送付されたWeb会議招待メー ルから所定の操作を行い、Web会議に参加します。 公証人は、公証人及び列席者との間で映像と音声が通じていることを確認した後、それぞれの列席者にマイナンバーカード等の本人確認資料を提 示してもらい、これをキャプチャして記録に残します。
なお、特に本人の意思確認が重要な場合には、 嘱託人に室内の状況をカメラで写してもらうなど、 本人の意思に影響を及ぼすおそれのある状況がないことを確認することがあるとのことです。
③意思確認と遺言公正証書案の記載内容が正確であることの確認
公証人は、嘱託人(遺言者)の意思確認と事 前準備の中で確定したWord証書案の確認の手続に入ります。 公証人は、Word証書の案文を公証人専用パソコンの画面に表示させた上、その画面が列席者(遺言者、証人2名)のパソコンの画面に表示されるよう面共有の操作をします。その上で、公証人がWord証書案を読み上げ、列席者(遺言者、証人2名)は自分の使用するパソコン画面に表示されたWord証書案を見ながら、公証人の読み上げを聞いて、Word証書案の内容が嘱託人(遺言者)の意思に即して正確に記載されていることを確認します。 確認後、公証人がWord証書案をPDF形式で保存してPDF証書案を作成します。
④列席者(遺言者、証人2名)の電子サイン
公証人の指示に基づき、所定の操作を行い、電子サインします。これを遺言者、証人2名の順に行います。
⑤公証人の電子サイン・電子署名と完成原本の 保存
列席者(遺言者、証人2名)の電子サインが終わると、公証人は、電子サイン・電子署名の手続を行い、公正証書原本を完成させ、公正証書原本を 電子公正証書システムに保存します。
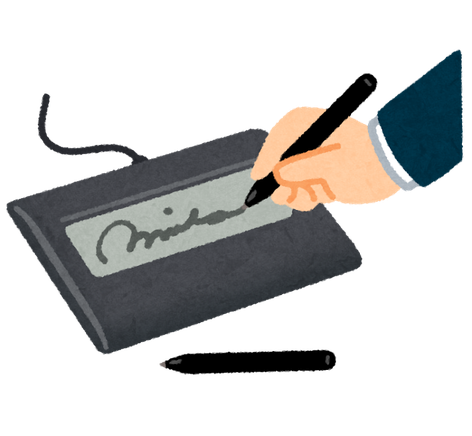
【正本・謄本の交付】
リモート参加者(遺言者)への紙正本・紙謄本の交付は、 手続終了後、郵送等の方法で行われることになります。
【電子正本・電子謄本の交付を希望する場合】
嘱託人(遺言者)が電子正本・電子謄本の交付を希望する場合は、クラウドシステムを利用した交付を行います。ただし、電子正本・電子謄本を用いて遺言執行手続き(相続登記、預貯金等解約手続き等)を行うためには、法務局や金融機関等の側で環境整備がなされていることが必要になるでしょう。
【注意点】
上記に説明した内容は、このブログを書いた時点(令和7年6月)での情報に基づいており、改正公証人法施行(令和7年12月)までに変更される可能性もありますので、ご注意ください。


